
【歯ぎしりがストレス解消に】そのメカニズムと弊害
ストレスが溜まると、無意識のうちに歯を食いしばる「歯ぎしり」をする人は多いものです。一見すると、単なる習慣的な動作に見えますが、実はこの歯ぎしりには、ストレス解消につながる深いメカニズムが関係しています。
歯ぎしりの際に働く「エンドルフィン」
歯ぎしりは、顎の筋肉を動かす運動にあたります。筋肉を使うと、脳内から「エンドルフィン」という物質が分泌されるのです。エンドルフィンには鎮痛作用と気分転換作用があり、歯ぎしりによってこのホルモンが出ることで、一時的に痛みや緊張がほぐれ、気分が落ち着くと考えられています。
つまり、歯ぎしりする行為自体が、ストレス解消の役割を果たしているわけです。これはストレスを発散する自然な行動であると言えるでしょう。
しかし、歯ぎしりが過度に続くと弊害に
歯ぎしりそのものが問題というわけではありませんが、歯ぎしりが常習化すると、様々な弊害が出る可能性があります。
- 顎関節への負担で顎関節症になる
- 歯や歯茎への過度な負担でトラブルが起きる
- 頭痛や肩こりなどの不調を引き起こす
- 睡眠の質が低下する
などです。過度な歯ぎしりが長く続けば、かえってストレスを増やす恐れもあります。
整体で歯ぎしりのケアを
そこで重要になるのが、歯ぎしりの習慣への適切なケアです。歯科医による口腔内のケアはもちろんですが、整体によるアプローチもとても有効です。
整体では、顎周りの筋肉のケアや関節の調整、全身のリラックスなどを行うことで、歯ぎしりの習慣の改善を図ることができます。筋肉の過剰な緊張をほぐし、無理のない顎の動きを取り戻せば、歯ぎしりの習慣が改善される可能性が高くなるのです。
歯ぎしりは、適度であればストレス解消につながりますが、過度に続けばかえって体に弊害があります。歯ぎしりの習慣がつきそうであれば、積極的にケアを心がける必要があります。整体を活用して、無理のない歯ぎしりのコントロールを心がけましょう。


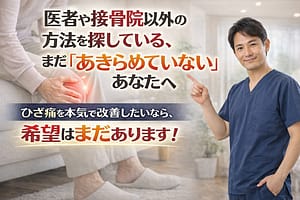

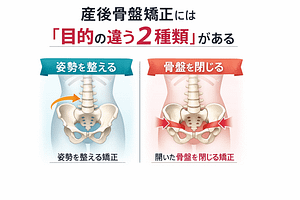

コメント